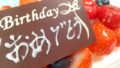源泉徴収票は転職や確定申告などの際に必要不可欠な書類ですが、いざ退職後に依頼しようとすると「どう頼めばいいの?」「メールで大丈夫?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、源泉徴収票をメールで依頼する際のマナーや例文、状況別の対応方法までをわかりやすく解説します。アルバイトや退職済みの会社への連絡など、よくあるケースごとの文例も紹介していますので、この記事を読めばスムーズに源泉徴収票を入手するための準備が整います。
この記事でわかること
- メールで源泉徴収票を依頼する際の基本的なマナーと書き方
- 状況別(アルバイト・退職後・再発行など)のメール例文
- メール以外の連絡手段との違いや注意点
- 新卒や収入103万円以下のケースでの注意事項
源泉徴収票のメールによる依頼例文に関する基本とマナー

源泉徴収票を依頼する機会は、特に退職後や転職時に訪れるものです。ですが、実際に「どうやって頼めばいいの?」「失礼にならない?」と悩む方は少なくありません。中でもメールで依頼するケースが多く見られますが、件名の書き方や文面のマナー、送るタイミングなど気をつけるべき点はたくさんあります。この記事では、そうした「源泉徴収票のメールによる依頼」に関する基本事項とマナーを丁寧に解説していきます。まずは、送るタイミングと送付方法の基本を押さえ、その上で、件名や本文の書き方、前職や退職後の依頼マナーについて詳しく見ていきましょう。
源泉徴収票を受け取るタイミングや送付方法の基本
源泉徴収票は、その年の収入や所得税の情報が記載された重要な書類です。多くの場合、退職後や年末調整の時期に必要になります。では、いつ、どのように受け取るのが適切なのでしょうか。まず、退職した場合は、退職日から1ヶ月以内を目安に送付されるのが一般的です。ただし、会社によっては事務処理の都合により遅れることもあります。そのため、必要な時期が決まっている場合は早めに確認し、適切に依頼することが大切です。
送付方法としては、通常は郵送が多く、稀に手渡しやPDFでの送信に対応してくれる会社もあります。ただし、個人情報を含む書類であるため、取り扱いには注意が必要です。メールで送付してもらえるかどうかは会社の方針次第となるため、丁寧に問い合わせる姿勢が求められます。また、メールで依頼する際は「いつまでに必要なのか」「送り先の住所やメールアドレス」を明記すると、相手にとっても対応しやすくなります。スムーズなやり取りのために、こうした基本事項はしっかり押さえておきましょう。
メールで依頼する際の件名や本文の書き方のポイント
源泉徴収票を依頼するメールを送るとき、まず大切なのが件名と本文の構成です。件名は一目で内容が分かるように簡潔にまとめるのが基本です。例えば「源泉徴収票送付のお願い」や「源泉徴収票のご依頼について」といった表現が適しています。あまりに長すぎる件名や曖昧な表現は避けましょう。本文は、まずは宛名から始まり、自己紹介(氏名・所属・在籍時期など)を簡潔に記載した上で、依頼の趣旨を明確に伝える構成にします。
例えば、「このたび転職先から提出を求められておりますため、源泉徴収票のご送付をお願いできれば幸いです」といった丁寧な言い回しが望ましいです。また、送付方法や送付先を明記することで、相手がすぐに対応できるように配慮しましょう。「下記の住所宛にご送付いただけますと幸いです」などの表現はとても丁寧で安心感があります。メールは短すぎても失礼に見えますし、長すぎても読みにくくなります。適度な分量と丁寧なトーンを意識しながら、誠実に依頼の意図を伝えることが大切です。
退職後や前職に対して源泉徴収票を依頼する際のマナー
退職後や前職に対して源泉徴収票を依頼する際には、特にマナーに配慮する必要があります。すでに会社を離れている立場である以上、相手に「お手数をおかけする」という意識を持って依頼することが基本です。メールの文面では、まずお世話になったことへの感謝を述べ、その後で源泉徴収票のお願いを伝える流れが自然です。例えば、「在職中は大変お世話になりました。さて、恐れ入りますが、源泉徴収票のご送付をお願い申し上げたく、ご連絡させていただきました」といった表現がよく使われます。
また、相手の業務を妨げないよう、必要な情報は簡潔に、かつ明確に伝えることが重要です。在籍時期や社員番号がわかっていれば記載すると、事務処理もスムーズになります。送付方法に関しては、相手の都合を最優先にしたうえで、「もし可能であれば〇〇していただけますと助かります」といった柔らかい依頼文にするのが望ましいです。最後に、「お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします」といった締めくくりも忘れずに。円満なやり取りのためにも、丁寧なマナーが大きな鍵となります。
源泉徴収票をメールで依頼する際の例文をパターン別に紹介

源泉徴収票を依頼する際の状況は人によって異なります。アルバイト先への連絡、退職後の郵送依頼、さらには紛失した場合の再発行など、それぞれに適したメール文面が必要です。相手との関係性や送るタイミングによって、表現やトーンを微調整することで、スムーズかつ丁寧なやりとりが可能になります。ここでは、よくあるシチュエーション別に、実際に使えるメールの例文を紹介していきます。特に、あまりかしこまりすぎず、かつ失礼のない依頼文を送りたい方は、文例を参考に自分の状況に合った形でカスタマイズして使ってみてください。
アルバイトや退職済みのバイト先に送る依頼メールの例文
アルバイトやパートで働いていた職場を退職した後、源泉徴収票が必要になる場面は多くあります。たとえば、就職先での提出や確定申告などがその例です。こうした場合には、以前のバイト先に源泉徴収票の送付をお願いすることになりますが、在籍期間が短かったり、連絡が久しぶりだったりすると、少し気が引けるかもしれません。しかし、相手に失礼なく伝えれば、ほとんどのケースで問題なく対応してもらえるので心配は不要です。
メールの例文としては、以下のような表現が適しています。
「お世話になっております。○月まで貴社でアルバイトとして勤務しておりました〇〇と申します。このたび転職先より源泉徴収票の提出を求められており、ご送付をお願いできればとご連絡いたしました。お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。」
このように、簡潔に自己紹介と依頼理由を述べることがポイントです。特に、複数のアルバイト先がある企業では、在籍時期を明記することで事務担当者の混乱を防げます。丁寧かつ控えめなトーンが好印象につながります。
郵送してもらう場合に適したお願いメールの書き方
源泉徴収票の送付方法として最も一般的なのが「郵送」です。退職後などで会社に直接取りに行けない場合、郵送をお願いするメールを送る必要があります。この際には、送り先の住所を正確に記載し、できれば返信用封筒の要否なども事前に確認しておくと親切です。企業によっては返信用封筒が必要な場合もありますので、問い合わせの際に「必要であればお知らせください」と添えるとスマートです。
例文としては、「お忙しいところ恐れ入りますが、源泉徴収票をご郵送いただけますでしょうか。以下に住所を記載いたしますので、ご確認の上ご対応いただけますと幸いです。」といった表現が良いでしょう。住所を文中に記載する場合は、改行を使い分かりやすく整えます。氏名、電話番号なども一緒に記載しておくと、万が一のトラブルにも対応できます。
大切なのは、依頼する側としての丁寧な姿勢と、相手が手間をかけずに対応できるような配慮です。返信が来ない場合もあるため、1週間程度待っても届かない場合は、再度連絡してみるのもひとつの方法です。焦らず、丁寧にやりとりを重ねていきましょう。
源泉徴収票の再発行をお願いする場合のメール文例
源泉徴収票を紛失してしまった、または届いていないという場合には、「再発行」をお願いする必要があります。企業側にとっても対応が必要な手続きとなるため、依頼する際には通常以上に丁寧な言い回しが求められます。特に、自分の不注意で紛失した場合には、その旨を簡潔に伝え、相手に迷惑がかからないよう配慮した文面が好まれます。
例えば、「先日、源泉徴収票をお送りいただきありがとうございました。大変申し訳ありませんが、私の不注意により紛失してしまいました。お手数をおかけして恐縮ですが、再発行をお願いできればと存じます。」というような表現が一般的です。必要に応じて再発行の手数料や切手代などを負担する意志を伝えると、より誠意が伝わります。
企業によっては、再発行に時間がかかることや、再発行そのものを受け付けていない場合もあるため、まずは「再発行の可否」についての確認から始めてもよいでしょう。メールの末尾には、「もし必要な手続きや費用がございましたらお知らせいただけますと幸いです」と添えるとスムーズです。再発行はあくまで特別な対応であることを意識し、感謝と配慮を忘れずに連絡しましょう。
源泉徴収票のメール依頼例文を使う際に注意したいポイント

源泉徴収票をメールで依頼する際には、ただ文例を使えばよいというわけではありません。状況や相手との関係性によっては、文面のトーンや連絡手段を変える必要もあります。また、収入額や就業期間によって、そもそも源泉徴収票が発行されないケースもあるため、自分の状況を冷静に確認することが大切です。ここでは、メール以外の連絡手段との違いや、言いづらいと感じるときの対処法、そして新卒や年収103万円以下の場合の注意点など、源泉徴収票のメール依頼に関する実用的なポイントを詳しくご紹介します。
手紙やLINEや電話といった他の連絡手段との違い
源泉徴収票を依頼する際、多くの人はメールを選びますが、他にも手紙やLINE、電話などいくつかの手段があります。それぞれの特徴を理解して使い分けることで、よりスムーズなやり取りが可能になります。たとえば、メールは文面を残せるため記録として残りやすく、事務的な依頼には適しています。相手の業務時間外に送っても失礼になりにくいのもメリットです。
一方で、LINEなどのチャットツールは気軽さがある反面、ビジネス用途としては適していない場合もあります。特に、公式な依頼や書類のやりとりには不向きとされるため、相手との関係性によっては避けた方が無難です。電話は即時性がある分、相手の都合を妨げない配慮が必要です。手紙は最もフォーマルですが、時間がかかるというデメリットがあります。緊急性がない場合や、メールアドレスが不明なときなどに選ばれる手段です。
それぞれの手段にメリットとデメリットがあるため、自分の状況と相手の立場を考慮し、最適な方法で依頼を行うことが大切です。
言いづらいと感じる場合に使える表現とテンプレート
源泉徴収票の依頼は、相手に手間をかける行為であるため、どうしても「言いづらい」と感じる方も多いでしょう。特に、短期間で辞めた職場や、人間関係があまり良くなかったバイト先などに連絡をするのは心理的に負担が大きいかもしれません。そんなときは、あらかじめテンプレートを用意しておくことで気持ちがラクになりますし、冷静に対応することができます。
使いやすい表現としては、「お忙しいところ恐れ入りますが」「ご多用の中恐縮ですが」など、相手の時間を気遣う一文を最初に添えることで、柔らかい印象になります。また、「ご対応いただけますと幸いです」や「お手数をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます」などの丁寧な締めくくりも有効です。
テンプレートを活用することで精神的なハードルを下げる効果があります。件名に「源泉徴収票送付のお願い」と明記し、本文では自己紹介・依頼理由・送付先・締めの挨拶の順で構成するのが基本です。「私は○月まで貴社で勤務しておりました〇〇と申します。このたび源泉徴収票が必要となり、ご送付をお願いしたくご連絡いたしました」といった形が標準的です。これらの定型文を活用しつつ、自分の状況に合わせて一部調整するだけでも、依頼の心理的ハードルは大きく下がるでしょう。
新卒や103万以下のケースや1月から3月の注意点
新卒や年収103万円以下の方、あるいは1月から3月の間に転職や退職をした方には、源泉徴収票の扱いに特有の注意点があります。まず、新卒の場合は、源泉徴収票を受け取るのが初めてという方も多く、会社から自動的に送られてくると思い込んでいるケースがあります。しかし、実際には依頼しないと送付されないこともあるため、必要に応じて自ら連絡をとることが重要です。
次に、年収103万円以下の場合ですが、この水準を下回ると源泉徴収票が発行されないこともあります。ただし、発行義務がないわけではなく、本人が希望すれば発行してもらえる場合がほとんどです。確定申告や扶養確認などで必要になる場合もあるため、必要な場合は遠慮なく問い合わせてみましょう。
また、1月から3月の期間に退職した場合、前年度と当年度の源泉徴収票が必要になるケースがあります。依頼時には「前年度分」と明記することで混乱を避けられます。いずれの場合も、相手任せにせず、自分の状況を正しく理解したうえで適切に依頼を行うことが、スムーズな取得につながります。
源泉徴収票のメール依頼例文に関するまとめ

この記事のポイントをまとめます。
- 源泉徴収票は退職後に必要となる大切な書類
- メールで依頼する場合は件名と本文を丁寧に
- 送付方法やタイミングを明記すると相手が対応しやすい
- 前職や退職後の会社にはマナーを守った表現が重要
- アルバイト先でも丁寧な依頼メールが基本
- 郵送を希望する際は住所や連絡先を明記
- 再発行には事情説明と感謝の気持ちが必要
- 手紙や電話との違いを理解し、状況に応じて選ぶ
- 言いづらいときはテンプレートを活用して気持ちをラクに
- 新卒や103万以下のケースでも遠慮せず確認を
源泉徴収票の依頼は、少し気を使う場面ですが、きちんとしたマナーと分かりやすい文章があれば、スムーズにやりとりが可能です。特に退職後やバイト先への連絡は気後れしがちですが、今回紹介した例文やテンプレートを活用すれば、自信を持って依頼できます。ぜひ自分の状況に合った文面を使って、正確に依頼を進めてみてください。